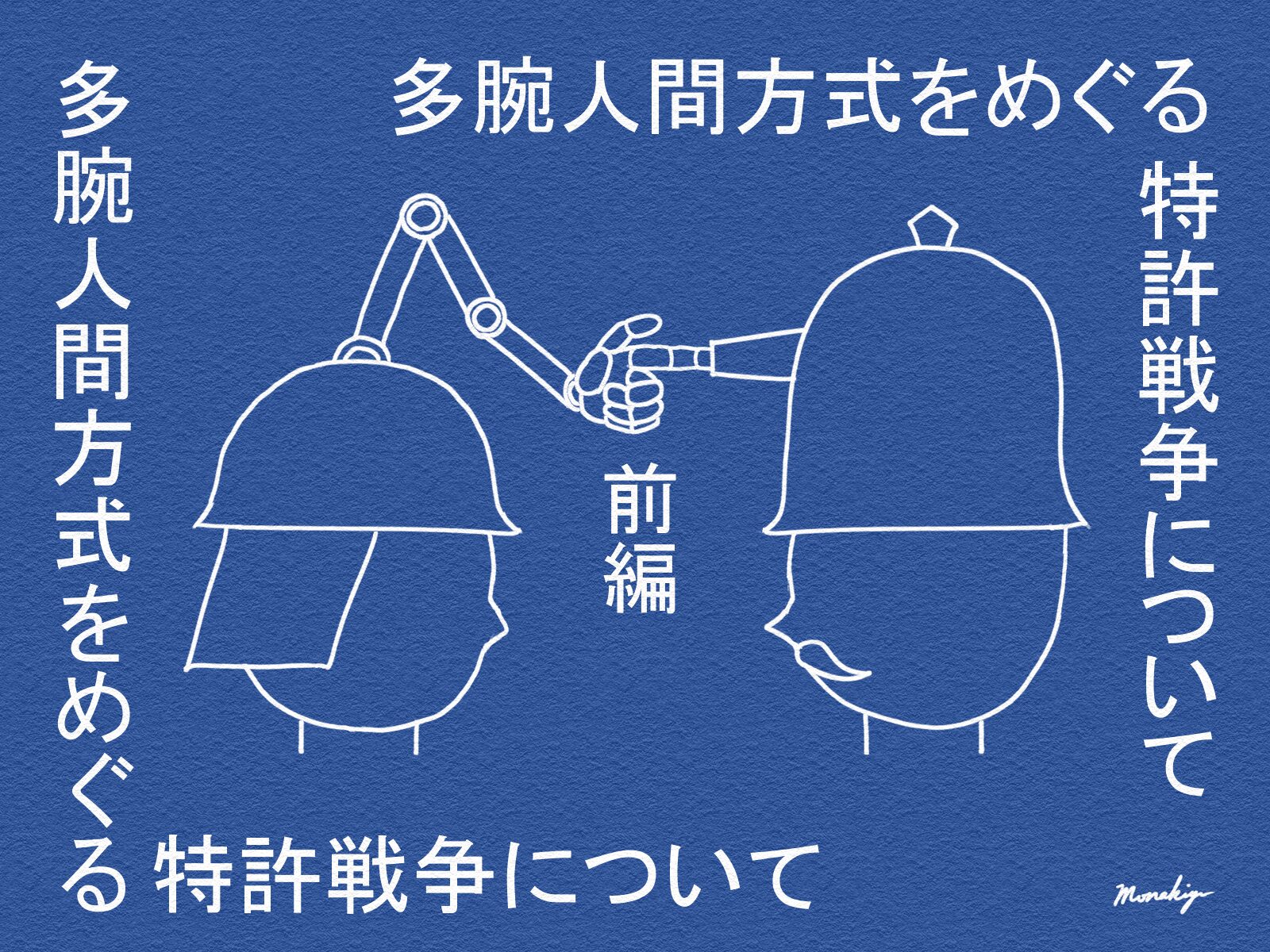小説『多腕人間方式をめぐる特許戦争について』の前編をお送りいたします。
※本作の内容はフィクションです。なお、本作(特に中編以降)は、海野十三著『特許多腕人間方式』のネタバレを含んでいます。 未読の方は、青空文庫『特許多腕人間方式』でご覧いただけます。
序
『特許多腕人間方式』という小説をご存じだろうか?
作者は日本SFの父と称される海野十三。
ある特許事務所に持ち込まれた世紀の発明『多腕人間方式』をめぐる物語である。
作者の海野十三は弁理士でもあった。そのため、小説『特許多腕人間方式』では、特許出願業務や拒絶対応などの場面がリアリティーを持って描かれている。
とはいえ『特許多腕人間方式』はあくまでもSF小説。したがって、そこで描かれている事象はフィクションであり、当然のごとく当該小説に登場する『多腕人間方式』なる発明も架空の存在である……はずだったのだが……。
特許
事の発端は、会社の後輩Sくんのつぶやきだった。
「なんだ、これ?」
隣席からの声に、わたしは彼のほうに視線を向けた。そのことに気がついたのか、Sくんは少しだけ恥ずかしそうな表情を浮かべてパソコンのディスプレイを指した。
「いや、なんか変なのが出てきちゃいまして……」
わたしはSくんの業務用パソコンを覗き込んだ。ディスプレイに『メモ書き』のスキャン画像が表示されている。
本特許は保管番号六四四号内公報一二七八号内に有ます。
特許第一〇〇四三三号ノ明細書及ヒ図面ハ特許法第六十三條但書二依リ公表ヲ中止ス
「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)に、これが?」
わたしが尋ねると、Sくんは「はい」と頷きを返した。
「『番号』は合ってるの?」
Sくんは「あっ」と小さく声を出してから頭をかく。
「すみません、誤入力です」
わたしは、そうだろうね、という感想を抱きつつ、ディスプレイに表示されている画像にふたたび視線を向けた。
わたしは某社の知的財産部門で働いている。特許公報の検索・閲覧は日常業務。その日々の業務で利用するのが『J-PlatPat』という特許情報システムなのだが、システムに入力する特許公報などの『番号』を誤ると、当然のごとく意図したものとは全く異なる文献が抽出されるのである。
「それにしても、きみは相変わらず『引き』が強いね。俺もこの仕事を長くやっているけど、こんなものを見るのは初めてだよ」
じつのところ、公報番号の入力ミスを含め、検索の結果が『思っていたものと違った』という事態に遭遇することは珍しくない。しかし、今回は『思っていたものと違った』だけではなく、検索結果そのものが『極めて特殊』だったのである。
「先輩でも見たことないとなると、かなりレアですね」
Sくんは嬉しそうにいってから、一転して真剣な表情になる。
「しかし『公表ヲ中止ス』というのは異常ですね……。特許出願の非公開制度って、まだ運用開始前ですよね?」
Sくんのいうとおりだった。『特許制度』とは、簡単にいってしまえば『発明公開の代償として一定期間の独占権を認める制度』なのである。したがって、制度上、本来的に発明は『公開』されなければならないのだ。つまり、特許検索に際して公報番号の入力ミスなどがあったとしても『思っていたものと違った明細書や図面』が出力されるのであって、『公表ヲ中止ス』などという『メモ書き』だけが出てくることは本質的にあり得ないのである。
ただし、一部の技術分野(たとえば、核関連技術など)には、公開すると安全保障の観点から問題が生じる発明も存在する。そのため、米国など諸外国には秘密特許制度が設けられており、日本でも令和6年5月1日から特許出願非公開制度の運用が開始される予定なのだった。
わたしはSくんに「よく勉強してるじゃないか」と冗談めかしていってから、ディスプレイに表示されている『メモ書き』を指した。
「この『特許第一〇〇四三三号』だけど、番号から考えてかなり古い特許のようだね。おそらく昭和初期のものなんじゃないかな。それが『公表ヲ中止』された……ということは?」
わたしが問う目を向けると、Sくんは「そうか」とつぶやいた。
「たしか戦前の日本にも秘密特許制度がありましたよね。それで公開されていないのですね」
「そうなのだろうね……。とはいえ、秘密特許制度そのものが戦後に廃止されているわけだから、本来は『特許第一〇〇四三三号』の明細書と図面もJ-PlatPatで閲覧できないとおかしいんだけどね……」
腕組みするわたしに、Sくんが好奇心に満ちた声音でいう。
「もしかして、いまだ公開できない秘密兵器、とかですかね?」
「いや、さすがにそれは……。単純に資料が散逸したか、あるいは、公報を電子化する際になんらかの不手際があったと考えるほうが自然なんじゃないか?」
わたしの答えに、Sくんは「現実はそんなものですよね」と残念そうに応じた。
次の瞬間、わたしのデスクの電話が着信音を響かせはじめた。
いきおい、わたしは通常業務に復帰した。
調査
退勤後、帰宅したわたしはリビングでノートパソコンを広げた。
「なになに、調べもの?」
と、妻がキッチンから駆け寄ってきてパソコンを覗き込む。わたしは彼女に、この日Sくんと交わした会話について説明した。
「……で、後輩に嘘を教えているといけないから、一応、調べてみようと思ってね」
わたしがいうと、妻は「相変わらず変なところで真面目だよね」と呆れたようにいって、キッチンに戻っていった。
わたしは記憶を頼りにJ-PlatPatでの検索作業を開始した。
「たしか特許番号は『一〇〇四三三』だったよな……」
はたして、ノートパソコンの画面に『特許第一〇〇四三三号ノ明細書及ヒ図面ハ特許法第六十三條但書二依リ公表ヲ中止ス』という例の『メモ書き』が表示された。
では、問題の『特許第一〇〇四三三号』は、いつごろ特許されたのだろうか?
わたしは、『特許第一〇〇四三三号』の前後、すなわち『特許第一〇〇四三二号』と『特許第一〇〇四三四号』の特許日を調べてみた。
「ビンゴ!」
特許第一〇〇四三二号: 特許 昭和八年四月五日
特許第一〇〇四三四号: 特許 昭和八年四月五日
『特許第一〇〇四三三号』が、前後の特許と同日――昭和八年四月五日――に特許されたのであろうことは疑いようがなかった。
あとは『特許第一〇〇四三三号』が『公表ヲ中止』された理由だ。
これについては、問題の『メモ書き』に『特許法第六十三條但書二依リ』と明記されている。
したがって当時の特許法を確認してみれば判明するはずだ。
わたしは国立公文書館デジタルアーカイブにアクセスして『特許法改正・御署名原本・大正十年・法律第九十六号』を閲覧した。
第六十三條 特許局ハ特許公報及特許發明明細書ヲ發行シ本法ニ規定スル事項其ノ他特許發明ニ関スル必要ナル事項ヲ之ニ記載スヘシ但シ軍事上秘密ヲ要スル特許發明ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
『但シ軍事上秘密ヲ要スル特許發明ニ付テハ此ノ限ニ在ラス』
間違いない。やはり『特許第一〇〇四三三号』は『軍事上秘密ヲ要スル特許發明』すなわち『秘密特許』だったのだ。
わたしは満足感とともに、キッチンの妻に声をかけた。
「どうやら後輩に嘘を教えてはいなかったみたいだよ」
彼女は夕食の味見の最中だったらしく、口をもぐもぐさせながら、ひらひらと手をふり返した。
依頼
それから数日後の夜、旧友のTくんから電話がかかってきた。
Tくんは大手電機メーカーに勤務するエンジニアなのだが、『名探偵に憑依される』という『災難』に見舞われたことを契機に現在は『推理を用いて諸問題の解決を図る』という『名探偵業』なる副業にも勤しんでいる。
「邪馬台国の件では、いろいろと助かったよ」
Tくんの言葉どおり、昨年わたしは彼の助手として邪馬台国の謎の解明に挑んだのだった(詳細は『小説・女王国の夜明け』をご覧いただきたい)。
もしかしたら今回も彼の『名探偵業』を手伝うことになるのではないか――そんな予感とともにTくんの次なる言葉を待つ。はたして……
「副業の件で、ちょっと相談に乗ってもらいたいことがあってね」
そら来た! わたしは気分が浮き立つのを感じた。
というのも、わたしはミステリー愛好家なのである。したがって『名探偵』なる存在と関りを持てることに多少の喜びを感じてしまうのは仕方がないことなのだ(もちろん、Tくんが本当に『名探偵』に憑依されているのか、その真偽のほどは定かではないのだが……)。
「また、なにか調べてくればいいのか?」
邪馬台国の謎に挑んだ際には、彼の要請に従って、わたしは国会図書館で1970年代の雑誌記事を探したのである。今回も同様の調査を依頼されるのではないかと考えたのだ。
「いや、今回は調べものをお願いしたいわけじゃないよ。きみに教えてもらいたいことがあるんだ」
意外ではあったが、口頭で済むのであれば、これほど楽なことはない。
「なにについて?」
「秘密特許について教えてもらいたいんだ」
秘密特許に関しては数日前に調べたばかりである。これがいわゆる『シンクロニシティ』というやつか、などと考えていると、Tくんが続けていった。
「戦前の秘密特許で、今日まで公開されていないものはあるだろうか?」
ますますもって偶然とは恐ろしい。いや、これは偶然ではないのかもしれない。もしかしたら『最適なタイミングで最適な疑問を提示する』というのも、名探偵の能力のひとつなのではないだろうか。
もしも後輩Sくんとの数日前のやり取りがなければ、わたしは「戦前の特許発明で現在も公開されていないものなんて、あるわけがない」とTくんの質問を一蹴していただろう。しかし、いまのわたしなら別の回答を提示できるのである。
「制度上――あるいは意図的に――いまも隠されている戦前の特許発明はないだろうね。ただし、なんらかの理由――たとえば資料の散逸やデータベース構築の際のミスなど――で、その内容を確認できない特許発明は存在するかもしれない……」
わたしは、例の『メモ書き』のみが公開されていた『特許第一〇〇四三三号』についてTくんに説明した。
「なるほど……。となると、今回の件は少々骨が折れそうだな……」
Tくんは、そう応じてから、沈黙した。
わたしは堪らずTくんに尋ねた。
「いったい、どんな特許について調べているんだい?」
Tくんはしばらく無言のままだったが、やがてぽつりといった。
「特許多腕人間方式……」
今度はわたしが無言になる番だった。
前編・完(中編につづく)