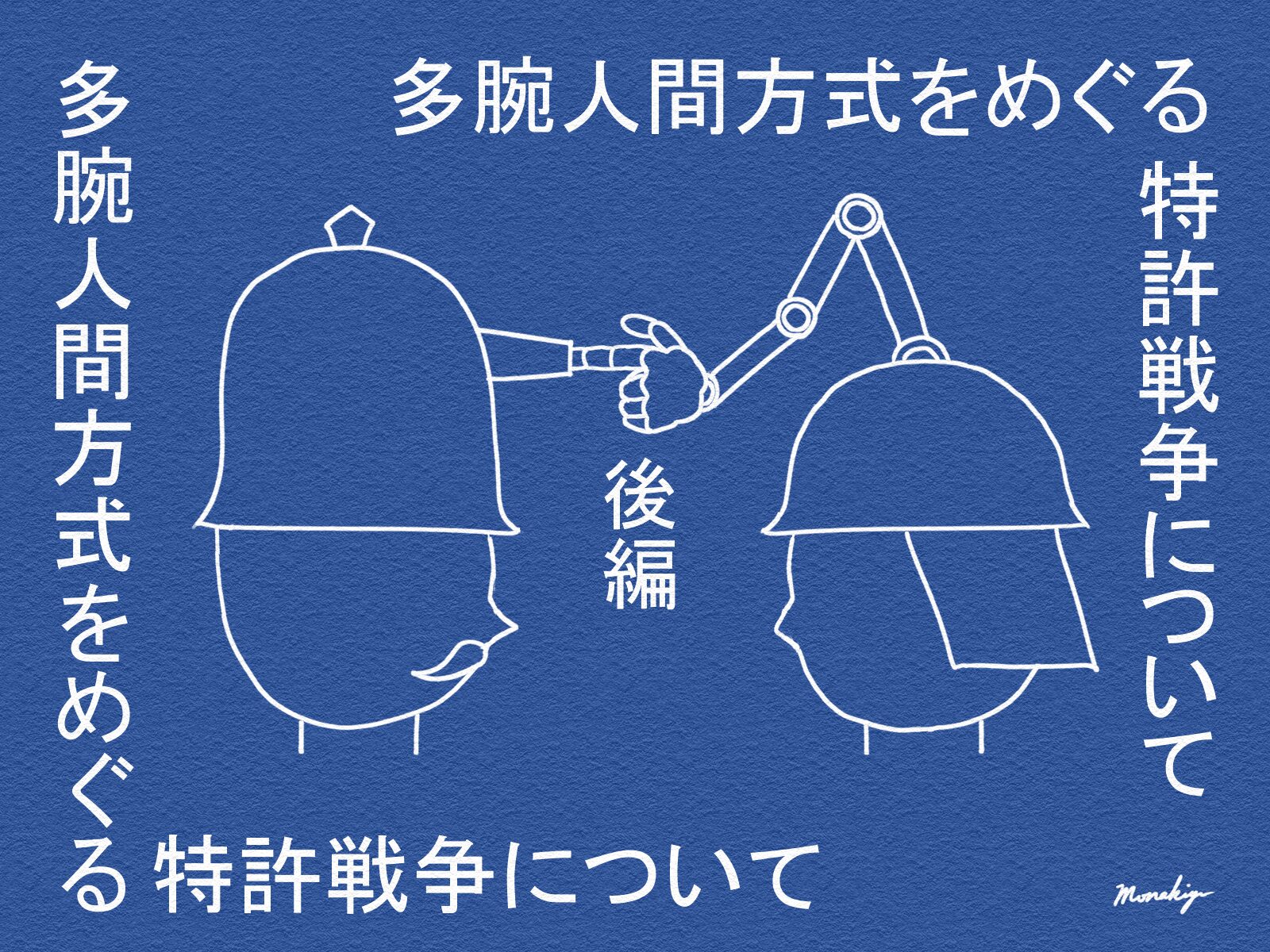小説『多腕人間方式をめぐる特許戦争について』の後編をお送りいたします。
※本作の内容はフィクションです。なお、本作は海野十三著『特許多腕人間方式』のネタバレを含んでいます。 未読の方は、青空文庫『特許多腕人間方式』でご覧いただけます。
『特許多腕人間方式』をめぐる謎。
わたしは、知的財産に関する知識に基づいて、その謎を解明したはずだった。
しかし、名探偵Tくんは異なる見解を有しているようで……。
推理
М氏との面談の翌週。わたしとTくんは、新宿駅ちかくの居酒屋で杯を重ねていた。
「……で、多腕人間方式をめぐる特許戦争について、きみはどう考えているの?」
わたしが問うと、Tくんは「それなんだけどね……」と困り顔で応じた。
「俺は、そもそも『多腕人間方式をめぐる特許戦争』なんてものは存在しなかったのではないか、と考えているんだ」
「えっ!?」
わたしは危うく日本酒の猪口を取り落としそうになった。
「先日の面談のあと、俺のほうでも少しばかり調べてみて、そういう結論に至ったんだよ」
たしかに、先日のM氏との面談の際、Tくんは「少々調べてみたい事項がある」といっていた。
Tくんは、とくに昭和16年に海野十三が発表した小説について調査したのだという。
「それはつまり、『特許多腕人間方式』以外の昭和16年に発表された小説について調べた、ということだね?」
Tくんは「そのとおり」と頷きを返してから、
「で、見つけたのが『人造人間戦車の秘密』という小説なんだ」
Tくんによれば、小説『人造人間戦車の秘密』は、昭和16年発行の雑誌『新青年』に掲載されていたらしい。新兵器発明王・金博士の活躍を描いたシリーズの2作目ということなのだが……
「その小説が、今回の件と関係があるのかい?」
「大いにあるよ。М氏の祖父・義三少年が父親に『陸軍での仕事内容』について質した際のことを思い出してみてくれ」
昭和16年のこと、М氏の祖父・義三少年は、兄が所有していた雑誌『現代』に『特許多腕人間方式』が掲載されていることを偶然発見した。そして『特許多腕人間方式』の、三本目の腕を兵器に転用するというアイデアに感激し、父親(М氏の曽祖父)に「お父様も陸軍で海野十三の空想科学小説に出てくるような兵器を開発されているのですか?」と質問した。
息子からの問いを受けて、父親は『問題の小説』を読むために息子の部屋に消えていった。
息子の部屋から戻ってきた父親は、真剣な表情で、義三少年に対して「父の研究については決して口外しないように」と厳命した……。
「……たしか、そんな話だったね」
わたしが確認すると、Tくんは深く頷いたのだが、
「その『問題の小説』というのが、まさに『問題』なのだよ。もしもそれが『特許多腕人間方式』ではなく『人造人間戦車の秘密』だったとしたら?」
「いやいや、義三少年は『特許多腕人間方式』の内容に感激して父親に質問したのだから、父親が読んだのも当然『特許多腕人間方式』のはずだろう」
「それが違うんだな。というのも、義三少年は父親に『お父様も陸軍で海野十三の空想科学小説に出てくるような兵器を開発されているのですか?』と質問しているだけだ。つまり、ここでいう『海野十三の空想科学小説』が『特許多腕人間方式』だとは一言もいっていない。さらに、義三少年は、兄が所有していた雑誌『現代』に『特許多腕人間方式』が掲載されていることを偶然発見したのだよ。ということは、雑誌『現代』は、兄の部屋もしくは兄の書棚にあったということになる……」
Tくんは、ここまでは問題ないだろうね、とでも言いたげな表情でこちらを一瞥してから、つづけて語った。
「一方で、義三少年の質問を受けて父親が確認したのは、義三少年の部屋もしくは義三少年の書棚だったはずだ。当然のごとく、そこに雑誌『現代』はない。したがって、そのとき父親が目にした海野十三の小説は『特許多腕人間方式』以外の作品ということになる」
「なるほど、それで同時期に発表された海野十三の小説について調査したわけだね。そうすると、父親が『特許多腕人間方式』を読んで顔色を変えた、というのは義三少年の誤解だったということになるね……」
「子供というのは、自分の見ている世界が全てだと思いがちだからね。自分が『特許多腕人間方式』を念頭に質問したのだから当然父親のリアクションも同じ小説に基づいているに違いない、と考えてしまうのも無理からぬことだろう」
「それにしても『人造人間戦車の秘密』とはね……。父親が、そんな物語を深刻に受け止めるものだろうか?」
「М氏の曽祖父は鬼籍に入るまで陸軍での業務内容を語らなかったほどの秘密主義者だった。つまり、秘密漏洩には人一倍気を使っていたはずなんだ。そんな人物が、息子から自身の仕事について問われ、その上『人造人間戦車の秘密』なんてものを発見したとしたら……そりゃあ顔色も変わるだろう、と俺は思うがね」
「どうしてだい? まさか、М氏の曽祖父が『人造人間』の開発に従事していた、なんてことを言い出すのではないだろうね」
わたしが冗談めかしていうと、Tくんは「おしい」と笑って、
「彼が開発していたのは『人造人間』ではなく『戦車』だよ」
わたしは「戦車……」とつぶやいてから、Tくんがそのように考える根拠を尋ねた。
Tくんが最初に言及したのは、昭和16年に交わされたというМ氏の曽祖父と同僚技師との会話の内容だった。
十数年ぶりに協働することになったМ氏の曽祖父と同僚技師は「『イゴウ』とは奇妙な縁を感じますな」と語り合っていたということだが……
「まず、残念なお知らせになるが、『イゴウ』が特許用語だというきみの推理は間違いだ」
Tくんに指摘されるまでもなく、М氏の曽祖父が『戦車』を開発していたのであれば――すなわち『特許多腕人間方式』とは何ら関わりがなかったのならば――、先日わたしが見当ちがいの推理を開陳してしまったことは明白なのだった。
では、М氏の曽祖父あるいは同僚技師の「『イゴウ』とは奇妙な縁を感じる」という発言の真意は、なんだったのだろうか?
わたしがそのことを問うと、
「じつは旧陸軍では、一番目の開発兵器に『イ号』、二番目の開発兵器に『ロ号』というように、イロハの順番に名前をつけていたんだ。つまりМ氏の曽祖父と同僚技師は、昭和16年と、その十数年前の、二度にわたって『イ号』の開発に携わっていたのさ」
「一番目の開発兵器が『イ号』なのだとしたら、十数年の時を経てふたたび『イ号』を開発するというのは変じゃないか?」
「ところが、ぴったりと符合する兵器が存在したんだよ」
「それが戦車?」
「そうなんだ。日本初の国産制式戦車である『八九式中戦車』――昭和3年に開発がはじまったその戦車の秘匿名称が『イ号』だったのさ。そして13年後の昭和16年に開発がはじまったのが、秘匿名称『オイ車』すなわち『大型戦車イ号』なんだ」
「中型戦車の『イ号』と大型戦車の『イ号』というわけか……。М氏の曽祖父と同僚技師は『八九式中戦車』と『オイ車』の両方の開発に従事していたのだね」
「そう考えると、М氏が語った他の事項についてもすべて説明がつくんだよ。たとえば、М氏の曽祖父が従事していた開発計画は戦時中に頓挫したという話だったが、じつは昭和16年に開発がはじまった『オイ車』も完成に至ることはなかったんだ。昭和18年に実施された初めての走行試験で破損、翌19年には解体されているんだよ」
さらにTくんによれば、『オイ車』は、主砲塔1基、副砲塔2基、後部銃塔1基を備える多砲塔戦車として計画されていたらしい。
「主砲塔1基、副砲塔2基、後部銃塔1基……。なるほど『火器を四つ持たせてやれる』という言葉は、そのことを意味していたわけだね」
М氏の曽祖父は自身の開発兵器について「いくら火器を四つ持たせてやれるといっても、用兵思想が昭和16年ならぬ1916年から変わっていないのだから、あれが完成したところで結局役には立たなかっただろう」と語っている。どうやら、その発言の前半部分については、彼が『オイ車』を開発していたと考えれば説明がつきそうだ。では後半部分はどうなのだろうか?
「М氏の曽祖父は『用兵思想が1916年から変わっていない 』とも発言していたのだったね?」
わたしが確認すると、Tくんは「その発言についても説明可能だ」と応じてから、
「陸軍では、『オイ車』を部隊の最前列に配置して敵の防御陣地に突入させるという運用を想定していたらしい。そして、世界初の戦車『マークI』も、デビュー戦――ソンムの戦い――において同様の使われ方をしているんだよ」
「もしかして、そのデビュー戦が?」
「うん、1916年9月15日のことだったのさ」
「つながったね。しかし、そうだとすると1916年の『ヘルメット銃』の特許は、今回の件とは何ら関係がなかったということになるね……」
わたしがいうと、Tくんは微笑をうかべて「そのようだね」といってから、
「ようするに、『機械腕』云々という話は、義三少年の誤解に端を発した『妄想の産物』に過ぎなかったというわけさ」
そう結論したのだった。
幕引き
「では、『曽祖父様は戦車を開発されていたようです』とМ氏に伝えて、本件は落着というわけだね。М氏には残念な結果になってしまうけど」
わたしは日本酒の徳利をTくんの手元に差し出した。
Tくんは「おっ」と声を漏らして猪口で日本酒を受けてから、
「まあ、残念な結果には違いないだろう。М氏は俺たちに『多腕人間方式をめぐる特許戦争』の存在を信じさせたかったようだからね」
と応じて、ニヤリと笑った。
「信じさせたかった?」
「そうさ。面談でのМ氏は、話題が『特許』や『機械腕』に向かうように、あからさまに議論を誘導していたじゃないか」
「それはМ氏が『多腕人間方式』の開発話を信じ切っていたからでは?」
わたしの問いに、Tくんは頭を振った。
「その可能性は低いだろうね。彼は『事前に色々と調査したが、結果は芳しくなかった』と語っていた。複数の調査結果が『多腕人間方式』の不存在を示していたのならば、普通は別の可能性を考えるはずだ」
「ということは、俺はМ氏の誘導にまんまと乗せられて『特許請求の範囲』だの『包袋禁反言』だのと得意げに語っていたわけか……」
わたしは過去の自分の姿をかえりみて頬が熱くなるのを感じた。
対するTくんは、
「まあ、詐欺師にかかれば、そんなものだろう」
と、至極冷静な口調でいった。
「詐欺!?」
わたしの羞恥心は、驚愕によって吹き飛ばされた。
Tくんは、わたしの驚きをよそに、
「『ないものをあるように見せる』というのは『投資詐欺』の典型的な手法じゃないか」
と、当然の事実を伝えるような調子でいう。
「きみは、いつ、それに気がついたの?」
「かなり早い段階で気がついていたよ」
「それにしては、面談の際、М氏と一緒になって随分と悩んでいたじゃないか」
「悩んだふりをしていただけさ。詐欺師というのは、ようするに犯罪者だ。怒らせると怖そうじゃないか」
「まったく名探偵が聞いて呆れるよ……」
わたしは、日本酒をぐいと飲んで、
「それにしても、俺たちのようなサラリーマンを騙してどうする? きみの懐事情は知らないが、少なくとも俺の財布には大した額は入っていないぞ」
少々情けない気分ではあるが、そう主張した。
Tくんは「俺もご同様だよ」と笑って応じてから、一転して真顔になる。
「М氏のターゲットは、もっと『大物』さ。おそらくどこかの社長か会長あたりだろう」
「じゃあ、なんのために俺たちのような『小物』を騙すんだ?」
「詐欺の『道具』にするためだよ。М氏は、架空の新兵器――多腕人間方式の現代版のような兵器――の開発計画をでっちあげて、投資を募ろうとしているのだろう。たしか、日本版の秘密特許制度は、今年の5月から運用開始ということだったね? 新たな法律が施行されるときには、新たな詐欺が横行するものだよ。ところで、兵器であっても、民生品と同様に、技術は累積的に進歩する。だから架空の新兵器をでっちあげるにしても、その基礎となる技術――あるいは歴史――が必要だ。それでМ氏は、存在するはずのない多腕人間方式の開発史を、俺たちに調べさせようとしたのさ」
「存在するはずのないものを調べても、なにも出てこないだろう」
「だから『道具』なんだよ。多腕人間方式の開発史について調査している人間がいる――М氏にとっては、そのこと自体が大切なのさ。というのも、誰かが真面目に調べているとなれば、架空の話であっても信憑性が増すじゃないか。しかも、不存在の証明は極めて困難だ。したがって、ターゲットを騙し切るまで、最終結論も出ない」
「そういうことか。最初にきみから電話がかかってきたときに『現在も内容を確認できない特許発明が存在する』と伝えたら、きみは『今回の件は骨が折れそうだ』といっていたね。あれは『公開されている特許を調べ尽くしても結論は出ない』という調査の困難性に対する嘆きだったのだね。それにしてもМ氏は、じつに狡猾だな……」
「そりゃあ詐欺師だからね」
「しかし、詐欺師ならば詐欺師らしく、架空の兵器の開発史もゼロから創作したほうが楽だったのではないだろうか……。どうしてМ氏は『オイ車』の開発話をベースにするような面倒なことをしたのだろう?」
「リアリティーのためさ。たとえば、М資金をめぐる有名な巨額融資詐欺があるだろ? あれも『隠退蔵物資事件』というベースとなる『実話』があるからこそ、多くの人が荒唐無稽な融資話を信じてしまうのだよ。つまり、『実話』を改変して架空の話を作り上げるほうが、ゼロから創作するよりも信憑性の高いストーリーを構築できるわけさ。ちなみに俺は、父親が多腕人間方式の開発に従事していると誤解した義三少年のエピソードは『実話』だと考えているんだ。というのも、М氏が語った内容のなかで、義三少年の話だけは血肉が通ったものだったからね」
Tくんは、そう語ってから「さて」とつぶやいた。
「これでМ氏から依頼された『推理業務』は完了したわけだが……、詐欺師というのは仕事の対価をきちんと支払ってくれるものなのだろうか」
Tくんは、そんな不安を口にしながらも、なぜか楽しげな様子で猪口の日本酒を飲み干した。
完