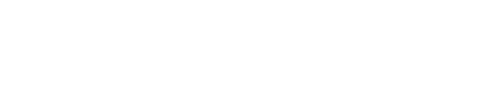小説『FBI ―架空捜査局―』の第4回をお送りいたします。
※本作はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。
架空捜査局(FBI)の野間崎捜査官から与えられた3つのヒント。
そこから名探偵Tくんが導き出した、新兵器――現代版『多腕人間方式』――の正体とは?
ついに本編最終回!
犬の手
「スヌーピーが根拠だって?」
私はTくんを正面から見据えた。
Tくんは私の視線をまっすぐ受け止めて首肯した。
そして、架空捜査局の野間崎捜査官が提示したヒント①~③と、それらに基づくこれまでの推理結果について語りはじめた。
- 『特許多腕人間方式』の一件においてTくんが導き出した『解決』は、非常に示唆に富んでいた
- 研究者たちは、すでに『アームズ』――すなわち『人の腕』――には見切りをつけている
- 新兵器の愛称は『きいち』
まずヒント①は、『リモート・ウェポン・システム』の存在を示唆していた。
次にヒント②は、問題の新兵器――現代版の『多腕人間方式』――の形状が『人の腕』とは異なること、および、当該新兵器が『無人兵器システム』であることを示唆していた。
そして、ヒント③は、文字どおり新兵器の愛称が『きいち』であるという情報と、この新兵器が『日本的』であるという情報を提示するものだった。
以上から、現代版の『多腕人間方式』は『自律型致死性兵器システム』のような国際的に議論のある『攻撃』兵器ではなく、『守り』に主眼をおいた『無人兵器システム』である、という推理が成立した。
また、『守り』すなわち『防衛』というキーワードに基づいて防衛装備庁のサイトを確認してみたところ、『小型無人機への対処』という目下の防衛上の課題も見えてきた。
「……以上のような次第なのだが、ここまで推理を進めた時点で、俺は野間崎氏から与えられたヒントに隠された『更なる情報』に気がついたんだ」
私は黙って話の先を促した。
「ポイントは、ヒント②の解釈だ」
と、Tくんは言葉をつないだ。
「ヒント②は新兵器の形状と性質を示唆するものだったわけだが……じつは、それだけではなかったんだ。というのも、野間崎氏はわざわざ『アームズ』という言葉と『人の腕』という言葉を併用している。そのことにも意味があったのさ。つまりヒント②は、新兵器においても『ARMS』と『人の腕』のような『言葉遊び』が成立していることを示していたんだ」
「その『言葉遊び』というのは?」
私が問うと、Tくんは、
「たとえば、次のような可能性はないだろうか?」
と告げてから、勿体を付けるように少し間をおいた。そして……
「研究者たちは、すでに『ARMS』には見切りをつけ、現在は『DOG・PAWS』に期待をかけている」
「ドッグ・パウズ?」
困惑する私に、Tくんは涼しい顔で応じた。
「『DOG・PAWS』は『犬の手』のことを指す英語だよ。つまり、研究者たちは『人の腕』には見切りをつけ、現在は『犬の手』に期待をかけている、というわけさ」
「いや、疑問なのはそこじゃなくて、『DOG・PAWS』というのは何なのか、という点だよ」
1980年代に研究されていたという『ARMS』の正式名称が『自動遠隔操作システム』であるのと同様に、新兵器の略称が『DOG・PAWS』であるのならば、それにも当然に正式名称が存在するはずだと、私は考えたのである。
「Drone Operator Guard and Protect Autonomous Weapon System――無人機操縦者防護用自律型兵器システム――の略称だよ」
Tくんは、そう告げてから、防衛装備庁のサイトで確認した『防衛上の課題』にふたたび言及した。
「いま、世界中の戦場でドローン兵器の有効性に注目が集まっている。一方で、人間の介入なしに標的を識別・選択し、殺傷力を持って交戦することができるような無人兵器システムの開発には議論がある。したがって、そのような無人兵器システムに対する評価が定まるまでは、小型ドローン兵器――より端的に言えば、長距離飛行ができないドローン兵器――が戦場に投入される際には、そのオペレーターも一緒に戦場に派遣されることになる。では、そのとき、戦場におけるドローン兵器の最も手近な攻撃対象は?」
と、Tくんが問う目を向けてくる。
しばし黙考してから、私は答えた。
「敵側のドローン兵器のオペレーターだろうか」
Tくんは、まさに、と首肯して、
「逆に言えば『いかにして敵ドローン兵器の攻撃から自陣営のオペレーターを守るか』という点が当面の防衛上の課題になるわけだよ。とはいえ、ドローン兵器の攻撃から身を守るのは、なかなか大変なんだ。たとえば、ドローン兵器から逃げ回りながら目視で撃ち落とすなんてことは、ほぼ不可能。そうなると必然的に、迎撃には人工知能の力を借りることになる。つまり『無人機操縦者』を「防護』するための『自律型兵器システム』が必要になるというわけさ」
「たしかに筋は通っているね。しかし……」
私は腕組みして、
「その『犬の手』というのは、どこから出てきたんだい? 『DOG・PAWS』という語呂合わせが正しいとすると、それを『多腕人間方式』の後継兵器だと解釈するのは難しいように思うのだが……」
かつての『ARMS』は、『人の腕』を模した構造とその名称の両面において、多腕『人間』方式に対応づけることができるものだった。
しかし、『犬の手』と称する兵器に、多腕『人間』方式との関連性を認めることはできるのだろうか?
私が疑問を口にすると、Tくんは頭を振った。
「『犬の手』だからこそ、『多腕人間方式』の後継兵器だと解釈できるのだよ。俺も最初は『無人』兵器システムを多腕『人間』方式に関連づけてよいものか、と疑問に思っていた。しかし『DOG・PAWS』という語呂合わせに想到したおかげで、その疑問が解消したのさ」
「つまり、『犬の手』という言葉に『人間』の含意がある、ということかい?」
私が問うと、Tくんは少し嬉しそうに口角をあげて……
「犬の手も人の手、だよ」
「うん?」
「きみだって、忙しいときには『犬の手も借りたい』と思うだろ?」
「それを言うなら『猫の手』じゃないか?」
私は肩をすくめた。
しかし、Tくんは笑みを浮かべたまま、
「人が借りたがるのは『猫の手』だけではなかったんだ。江戸時代に書かれた浮世草子に『犬の手も人の手にしたい程取り込んで居るをりなれば』という言い回しが出てくるのさ。で、面白いのがここからなんだ。その浮世草子のタイトルが、なんと……」
Tくんは前傾姿勢になって言葉をつないだ。
「……『鬼一法眼・虎の巻』なのさ」
鬼一法眼は、室町時代に書かれた『義経紀』に登場する伝説上の人物である。彼は文武の達人とされており、特に剣術については京八流の祖、剣術の神として崇められている人物だった。
「なるほど、鬼一か」
私は、ようやくヒント③の意味するところを理解した。
Tくんが満足げに頷きを返す。
「ご推察のとおり、新兵器の愛称である『きいち』は、『鬼一法眼』から取られたものだったのさ」
格闘戦
コーヒーカップから、ふたたび湯気があがっている。
もちろん、キリストよろしくコーヒーが復活したわけではない。コーヒー一杯で長時間話し込んでいることに気が引けて、お代わりを注文したのである。
熱いものが苦手な――にもかかわらずコーヒーはホットに限ると思っている――私は、恐る恐るコーヒーカップを口元に運んだ。
「相変わらず、猫舌は治らないようだね」
と、Tくんが笑う。
「猫舌というのは『治る』とか『治らない』とかいう種類のものではないらしいね」
と、私は応じてから、
「ところで、いまは『猫』よりも『犬』の話を先に進めるべきではないだろうか?」
Tくんは、違いない、と相槌をうって、
「先ほど言及した『鬼一法眼』なのだが、牛若丸――のちの源義経――に兵法を指南した『鞍馬天狗』だったという説があるんだよ」
「今度は『天狗』か……『犬』はどこに行ったのさ?」
「俺は『犬』の話をしているんだよ。『天狗』というのは『天』の『狗』と書くじゃないか」
「天の狗……。もしかして、それでパイロット姿のスヌーピーを持ち出してきたのかい?」
漫画『ピーナッツ』に登場するスヌーピーは、作品のなかで数々の扮装を披露している。そのなかでも、スヌーピーがパイロットに扮し、犬小屋の屋根で空を見上げて、撃墜王・レッドバロンとの空中戦を夢想するシーンは特に有名だった。
Tくんは深く頷いて、
「『ビーグル犬が空中戦の夢を見る』という場面が象徴しているように、かつて戦闘機の戦いは『ドッグファイト』が中心だった……」
Tくんによれば、第一次世界大戦前まで航空機は戦闘力を持たず、敵地の偵察に使われるのみだったらしい。しかし、航空偵察の重要性が認められ始めると、敵の航空偵察を妨害する必要が生じた。そして、敵航空機を駆逐するための航空機――戦闘機――が生み出された。
以降、戦闘機は、相手を捉えるために機動しながら戦う『空中アクロバティック戦』――犬同士が尻尾を追いかけあう姿に似ていることから『ドッグファイト』と名付けられた格闘戦――を展開することになった。
ちなみに、スヌーピーの宿敵、撃墜王・レッドバロンは、そんなドッグファイト全盛期の第一次世界大戦において活躍した、実在のドイツ軍人である。
「犬の戦いか……。それにしても、『きいち』という愛称が『天狗』につながり、さらに『戦闘機』につながるとはね。ということは、もしかして現代版の『多腕人間方式』というのは……」
このとき私の脳裏を掠めたのは、無数の小型ドローン兵器が戦地の上空で格闘戦を繰り広げている光景だった。
Tくんは私の想像を肯定するように、わずかに頷いた。そして端的に言語化した。
「いかにも、現代版の『多腕人間方式』の正体は『敵ドローン兵器を駆逐するためのドローン兵器』だというのが、俺の結論だよ」
後期クイーン的問題、ふたたび
「第一次世界大戦において敵航空機を駆逐するための航空機が求められたのと同じように、現在は敵ドローン兵器を駆逐するためのドローン兵器が求められているということか……」
と私は応じてから、疑問を口にした。
「しかし、迎撃用ドローン兵器の、どのあたりが『日本的』なのだろうか?」
Tくんは、少し斜め上に視線を向けて、
「たとえば『ドローンを以てドローンを制するという新兵器の戦い方が、盾を持たず刀で切り結ぶ、攻防一体の武士の戦法を想起させるから』という理由が考えられるね。なにしろ、鬼一法眼は剣術の神として崇められているのだから」
「なんと、またしても『きいち』につながるのか」
私が驚きの声をあげると、Tくんは嬉しそうに頷いて……
「さらに言えば、新兵器『きいち』はオートバイ――すなわち『鉄馬』――に搭載される兵装なのかもしれない。というのも、鬼一法眼は『義経紀』の登場人物であり、源義経といえば、言わずと知れた『騎馬』戦術の天才だからね。その上、日本には『人馬一体』という言葉がある。『人との一体性』を有している兵器であれば、『多腕人間方式』の後継という位置づけにも納得がいく。そして何より、昔から日本では二輪車で物品を輸送する装置の開発が盛んに行われてきた……」
「うん!?」
「蕎麦の出前でお馴染みの出前機だよ。出前機の発明者が東京の蕎麦屋だというのは、有名な話じゃないか」
Tくんが、そういって、にやりと笑う。
「蕎麦ならいざしらず、ドローン兵器のデリバリーというのは、いかがなものだろうか」
私は、出前用のオートバイの荷台からドローン兵器が飛び立つ様子を想像して、天を仰いだ。

「まあ、出前機というのは冗談だが……、真面目な話、ロシアではドローン攻撃に対処するためにバイク部隊の増強を図っているというし、アメリカでは特殊部隊の移動手段としてカワサキモータース製のミニバイクが採用されている。そのあたりの事情を考慮すると、ドローン兵器をオートバイで輸送するというコンセプトは、なかなか理にかなっていると思うんだ」
自信に満ちた声音でそう語るTくんに、私は、なおも頭の中を駆け巡るオートバイとドローンのイメージに翻弄されながら応じた。
「少なくとも野間崎捜査官が提示したヒントとは整合しているね。それにしても、わずかなヒントから、よくぞそこまで辻褄を合わせることができるものだ」
「まあ、名探偵だからね」
と、Tくんは優雅な手つきでカップを手にして、コーヒーを口にしたのだが……
「しかし『わずかなヒントから』という点が問題ではある」
そう呟いて表情を曇らせた。
「後期クイーン的問題のことを言っているのかい?」
私が尋ねると、Tくんは、残念ながら、と頷いて……
「野間崎氏が提示したヒントに基づいて『真の解決』を導き出せるのか――つまり、我々が推理に必要な情報をすべて入手できているのか――という点は不明。それどころか、野間崎氏が虚偽の情報を提示している可能性すらあるからね」
「後期クイーン的問題に始まり、後期クイーン的問題に終わる、というわけだね」
「なんとも締まらない話だが、そのようだ」
Tくんは、コーヒーカップをそっとテーブルに戻してから、言葉をつないだ。
「しかし、今回のことで、気づきを得られた点もある。名探偵の役割だよ。名探偵は『解決』という名の物語を提供しているに過ぎない――そのことに気がついたんだ」
「物語?」
「うん。名探偵の推理結果は、与えられた情報に基づいて構築された、ひとつの物語に過ぎない。そう解釈すれば、推理結果と『真の解決』とを切り離して考えることができる。たとえば、与えられた情報が虚偽であったとしても、物語は成立するからね」
「たしかに、一般的な漫画や小説の大半は、虚構に基づく物語だね」
Tくんは、大きく頷いて、
「そのとおり。大切なのは虚構性なんだ。名探偵というものは本質的に虚構性を備えているのだよ」
「つまり『名探偵は虚構性を備えているがゆえに、後期クイーン的問題を回避できる』というわけかい?」
「『後期クイーン的問題を回避できる』というよりも『後期クイーン的問題から逃避できる』と表現するほうが正確かもしれないけどね。しかし、情報の真偽が分かる超能力の存在や、メタレベルからの介入を期待するよりは、よほど健全な後期クイーン的問題の解決案ではないだろうか」
「その、メタレベルからの介入、というのは?」
「推理小説においては、作者の介入だね。作品の外に存在する作者が『解決に必要な情報はすべて揃っている』と主張し、さらに『これまで提示された情報に虚偽は含まれていない』と宣言すれば、万事解決というわけ。現実世界でいえば……神の介入、だろうか」
そう語ってから、Tくんは何事かに気がついた様子で口をつぐんだ。
そして、ぐるりと視線を彷徨させてから……
「君の説明によると、架空捜査局は文部科学省に設けられているということだったね?」
と、質問してきた。
私は頷きを返して、
「文部科学省の外局である文化庁が著作権に関する事項を所管しているから、というのが理由らしいよ」
Tくんは腕組みして、
「本当に、それだけだろうか……」
と、つぶやいた。
私が問う目を向けると、Tくんは、突飛な想像ではあるが、と断りを入れてから告げた。
「もしかしたら、神の介入――あるいは、それに類する事象――が現実に存在するのではないだろうか。それで宗教関係も所管している文部科学省に架空捜査局が設けられているのでは……。ふと、そんなふうに思ってね」
「なんだか大ごとになってきたね」
私がいうと、Tくんは真剣な顔で頷いたのだが、すぐに表情を緩めて……
「まあ、まったく逆の可能性もあるのだけどね」
「逆の可能性?」
「うん。架空捜査局などという組織は存在しない、という可能性だよ」
Tくんの言葉に、私は、はっとした。
野間崎捜査官――架空捜査局が存在しないのならば『捜査官』という呼称も改めなければならないのだが――によれば、架空捜査局は『文部科学省内でも限られた者しかその存在を知らない組織』とのことだった。
このときまで気がつかなかったのだが、そのような言説は詐欺師が多用する種類のものなのだった。
たとえば、M資金詐欺においても、秘密資金の管理団体として『財務省内でも限られた者しかその存在を知らない極秘組織』に言及されることが多いのである。
「神の次は詐欺か……」
私は頭を振った。
「神か、詐欺か、はたまた別の事実が存在するのか……真相は不明だが、いずれにしても架空捜査局に関して深入りするのは危険だろうね」
そう告げてから、Tくんはカップに手を伸ばし、残りのコーヒーを飲み干した。
そして、空になったカップを見つめたまま、ふたたび口を開いた。
「危険と言えば、後期クイーン的問題についても下手に手出しをしないほうが良さそうだ。『触らぬ神に祟りなし』とはよく言ったものさ」
そう語るTくんの声には、諦念の響きが含まれていた。
完