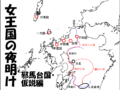小説『女王国の夜明け』の第二部『副業名探偵・誕生編』をお送りいたします。
- 本作を最初(第一部)からご覧になりたい方は、こちらからどうぞ。
副業として『名探偵業』をはじめるという旧友のTくん。
Tくんとの電話で、ようやく『名探偵業』なるものが『推理を用いて諸問題の解決を図る業務』であることを理解した、わたし。
しかし、わたしには、まだ疑問が残っていた。
『名探偵業』の最大の成立要件――それは名探偵の存在。
では、名探偵はどこにいるのか?
電話
Tくんは『名探偵業』をはじめようとしている。
しかし、その業務を遂行できるのは、名探偵だけである。
わたしは「名探偵はいない」と指摘したが、Tくんは自信たっぷりに「いる」という。
わたしは問わずにはいられなかった。
「いったいどこに?」
Tくんは、もったいを付けるように少し間をおいてから、
――想像の世界に
と答えた。
「……いや、さすがにそれは」
――なにか問題でも?
「問題ある。というか問題しかない。それを『いる』というのは反則だ」
――なぜだ? 想像の世界の住人だとしても、きちんと仕事をしてくれれば、それでいいじゃないか。
「きちんと仕事をしてくれれば、ね。だが残念ながら、想像の世界の住人というのは、俺たちのように日々の糧を得るために働いたりはしないのだよ」
――シャーロック・ホームズもエルキュール・ポアロも想像の世界の住人だが、ちゃんと働いている。
「実際に働いているのは、コナン・ドイルであり、アガサ・クリスティだ」
――エラリー・クイーンみたいな例もある。
「それは単に、フレデリック・ダネイとマンフレッド・ベントン・リーの共同ペンネームと、作中の名探偵の名前が、両方とも『エラリー・クイーン』というだけのはなしだ。つまり、ここでも実際に仕事をしているのは作者『エラリー・クイーン』であり、名探偵『エラリー・クイーン』は、その仕事の成果物にすぎない」
――しかし、そのあたりは、わりと曖昧なんじゃないか? ほら、よく作家が「キャラクターが勝手に動き出す」みたいなことをいうじゃないか。それが本当なら、想像上のキャラクターが作者の手を動かして小説を書かせている、とも解釈できるだろ?
「メタファーとしては面白いが、それを認めたとしても、結局のところ想像上のキャラクターは想像の世界を勝手に動きまわっているだけだ。こちらの世界の問題を解決するために出てきてくれるわけじゃない」
――普通はそうだ。でもこの世のなか、時として普通じゃないことが起こるんだよ。
「というと?」
――どうやら俺は、想像の世界から出てきた名探偵に取り憑かれているみたいなんだ。
「『取り憑かれている』という言葉には、『固執している』という意味と『憑依されている』という意味の二通りあると思うのだが……」
――後者だよ。俺は名探偵に憑依されている。
「……」
――もしかして、俺がおかしくなったと思ってる?
「ああ、ちょっとだけ……」
正直にいうと、ちょっとどころではなかった。
それはそうだろう。想像の世界から出てきた名探偵に憑依されている、などと真剣に語る人物が、まともであるはずがない。
さらにTくんの場合、「憑依」などという怪しげな事項を「副業」というリアリスティックな事項に関係づけて語っているのだから、事態は一層深刻だった。
わたしの胸中を察したのか、Tくんは
――まあ、おかしくなったといえば、そうなのかもしれないが……
と、つぶやいてから、彼が遭遇したという「事件」について語り始めた。
事件
一か月ほど前のこと、Tくんと妻のAさんはふたりで買い物に出かけたという。
Tくんはマイカーを所有していない。TくんもAさんも車の購入には否定的だったし、そもそも駅近のマンションに入居しているため基本的に移動には電車を利用するからだった。
その日も、TくんとAさんはマンション最寄りの中央線・K駅で電車を待っていた。
ほどなくして快速・東京行きがホームに到着した。
降車する人の波が落ち着いたのを確認し、Tくん夫妻は手を取り合って電車に乗り込もうとした。
そのとき突然、電車内で居眠りしていたらしい男が、はねるような勢いで立ち上がった。そしてTくん夫妻のほうに突進してきた。
Tくんは身構える暇もなく後ろに突き飛ばされ、そのままホームに転倒した。
ぶつかってきた男は「降りる人が先だろーが馬鹿! マナーを守れ!」と叫びながらホームを走り去っていった。
――いろいろと突っ込みどころはあると思うが、ようするに駆け出し降車の犠牲になったというわけさ。
「駅のアナウンスで『駆け込み乗車は危険です』というのはよく聞くけど、考えてみれば、その逆もかなり危険だよな……」
わたしは、Tくんに同情の意を表するとともに一応の見舞いの言葉を贈ってから、質問した。
「ところで、その一件でおかしくなったということは、やはり転倒した際に頭を打ったのか?」
――そのようだ。そして、それ以来どうもおかしいんだ。
「頭が?」
――うん……。働きすぎるんだよ。
「はあ!?」
――頭が働きすぎるんだ。
「それはわかった。というか日本語としての意味はわかる。ただ、どういうことなのかがわからない……」
――以前よりも物事を観察できるようになったのさ。ちなみに、ここでいう観察は、シャーロック・ホームズがいうところの観察のことだ。“You see, but you do not observe.” という有名なセリフがあるだろ?
「君は見ている、でも観察していない。そのセリフが出てくるのは、たしか『ボヘミアの醜聞』だったな」
――ご名答。ホームズが指摘しているとおり、俺たちは日常的に多くの事物を目にしているが、だいたいは見ているにすぎず、観察なんてしていない。ところが、事件の直後から、とにかく色々と観察できるようになったんだ。
「なるほど、それで実際にどんなものを観察したの?」
――まずは、自分自身かな。なぜ自身の内面に劇的な変化が起こったのか、それを解明したいと思ってね。
「で、観察の結果は?」
――名探偵に取り憑かれている、ということが判明した。
「そうだった……そのはなしだったわ……」
わたしはスマートフォンを片手に天をあおいだ。
「……しかし、想像上の存在である名探偵が憑依しているというのは、いくらなんでも突飛すぎないか?」
――逆だよ。想像上の存在だからこそ、憑依するのさ。たとえば、憑依現象の代表例である『狐憑き』だって、本物のきつねが取り憑いているわけじゃない。取り憑いているのは「きつねは特別な霊力を持っている」といった伝説に基づいて人間の心が生み出した想像上のきつねだ。
「……一応、筋は通っている」
わたしは、とりあえずTくんの説明を受け入れることにした。
他者の心の中で実際に何が起こっているのかは誰にもわからない。だから、Tくんの説明を受け入れざるを得なかった、というのが正確な表現かもしれないが。
ただ、Tくんのはなしを受け入れることで、様々な事柄の関連性が見えてきたことも事実だった。
「なるほど、『名探偵業』というのは、こちらの世界に出てきた名探偵を副業に活かすために生み出された。そして、その名探偵の能力を試すために、過去に多くの名探偵が取り組んだ邪馬台国の謎の解明に着手した、というわけか……」
――名探偵の力をもってすれば、小遣いを増やすことなんて朝飯前だと思っていたんだけどね。でも実際には、邪馬台国の謎の解明に随分と時間がかかってしまった。それで、きみに手伝ってもらいたいと思って連絡したんだよ。
「名探偵の手伝いねぇ。ということは、俺の役回りはワトソン?」
――邪馬台国の秘密に迫ろうというのだから、神津恭介に対する松下研三のほうが適切だろうね。
「いずれにしても推理をありがたく拝聴するお役目を果たせばいいわけだな」
――まあ、そういわないでくれ。もう四十代にもなると、この手のはなしに付き合ってくれる友人は少ないんだよ。それに、ワトソンにしても松下研三にしても、単に推理を拝聴しているわけじゃない。常識人の観点から名探偵の推理を検証するという大事な役割も果たしている。俺が求めているのも、単なる聞き役ではなく、彼らのような検証能力を持った友人なのさ。
「なんだか、おだてられているような気もするが……」
そうつぶやいてから、わたしは、はたと気がついた。
「ちょっと待ってくれ」
わたしは、考えを整理してから、Tくんに訊いた。
「さっき、きみは、邪馬台国の謎の解明に随分と時間がかかってしまった、と過去形で語っていた。さらに、推理を検証する友人が必要だ、ともいった。ということは……邪馬台国の謎に関する推理はすでに完了していて、検証すべき答えも出ている!?」
Tくんは、もちろん、と応じてから告げた。
――俺の推理……いや、俺に憑依している名探偵の推理なのかな……とにかく推理によれば、邪馬台国は……
わたしは、つづく言葉を聞き逃すまいと、全神経を耳に集中した。
第二部・完(第三部『邪馬台国・仮説編』につづく)
※本作の登場人物であるTくんのモデルは、当ブログ『もなきよの創作プロトタイピング』を運営するわたしの実在の友人です。ただし本作の内容は、あくまでも創作です。