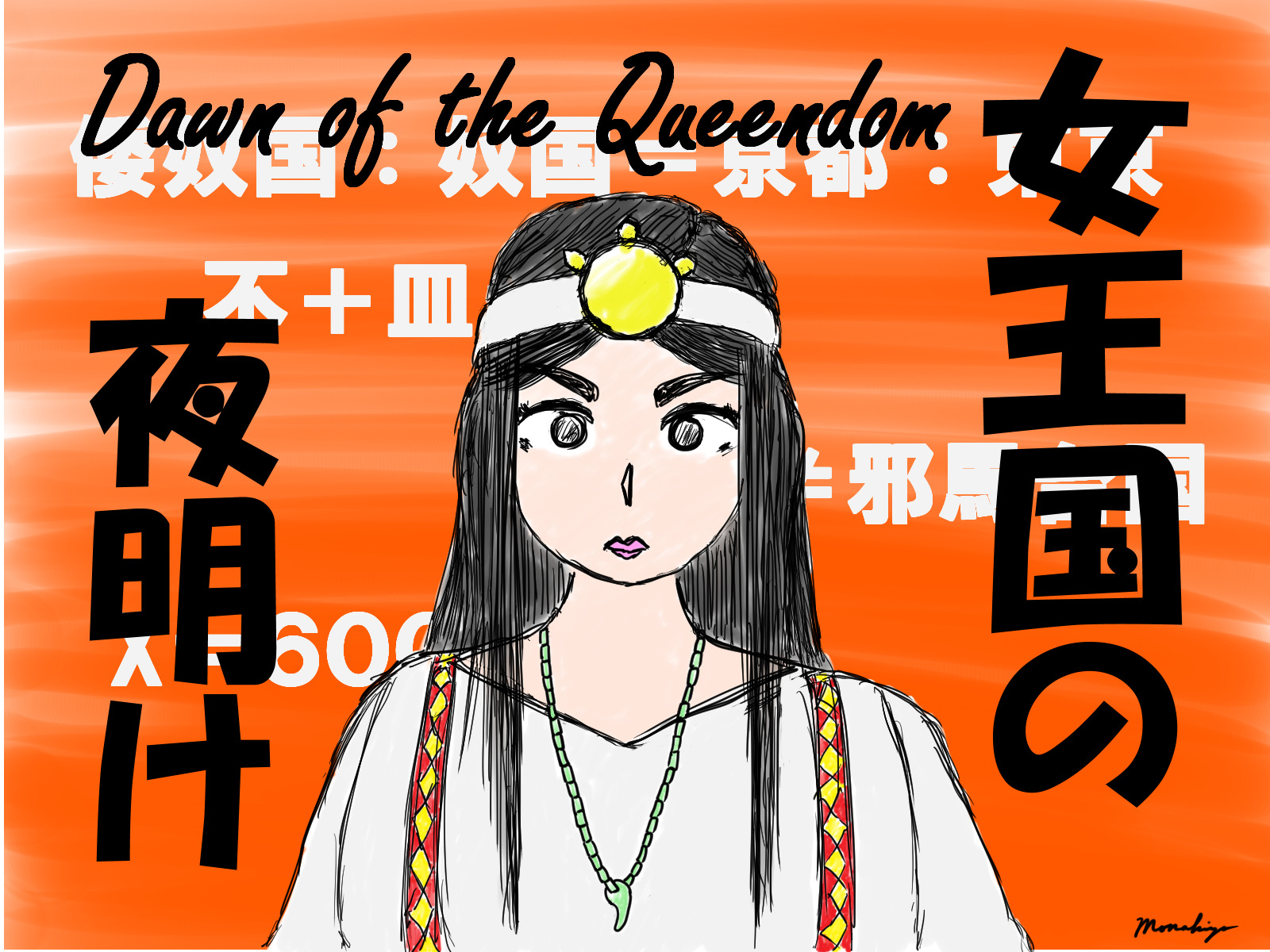小説『女王国の夜明け』の第六部『邪馬台国・論理編』をお送りいたします。
帯方郡を発った魏使は、狗邪韓国、対馬国、一大国を経て、末盧国(現在の唐津)に上陸。その後、有明海沿岸部にむけて陸行した!
名探偵Tくんの推理において、魏使は通説のルートから大きくはずれ、さらに奴国、不弥国にむかって驀進する!!
倭奴国:奴国 = 京都:東京
Tくんの推理によれば、『魏志倭人伝』に記されている『伊都国』は佐賀県小城市牛津町の周辺に存在したらしい。
『天之葺根命』を『伊都国王』の象徴とみなし、さらに『天之冬衣神』を『いと』と関連づける論理展開は強引に過ぎるが、唐津から牛津に至るルートが『魏志倭人伝』の『東南陸行』記事と完全に整合している点は評価すべきだろう、とわたしには思われた。
わたしは、伊都国の比定地については一応納得した旨を伝え、Tくんに話を先に進めるよう促した。
Tくんは、ジョッキに残ったビールを飲み干してから、「では、次は奴国だな」と、うれしそうにいった。
東南奴国に至る百里。官を兕馬觚といい、副を卑奴母離という。二万余戸あり。
石原道博編訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝(1)―』
「伊都国から奴国への行程について、『魏志倭人伝』は『東南奴国に至る百里』と記しているね。末盧国から伊都国が『東南陸行五百里』だから、伊都国から奴国までの移動距離は、その五分の一か」
と、わたしが確認すると、Tくんは「そういうことになるね」と応じてからつづけた。
「唐津(末盧国の比定地)から牛津(伊都国の比定地)までの距離は約35km。これが『五百里』に相当するとしたら、その五分の一の『百里』は約7kmということになる。だから俺は、牛津から東南に約7km移動したところに奴国が存在したと考えているんだ」
「牛津から佐賀平野を陸行したわけだね?」
「いや、陸行ではないよ。弥生時代には、まだ縄文海進の影響が残っていた。だから当時の有明海の海岸線は、いまよりもずっと内陸側にあったんだ」
「そうだった、牛津も入江だったんだよな。ということは、移動は船?」
「そう考えるべきだろうね。『魏志倭人伝』の『一大率』に関する記述を思い出してみてくれ。『皆津に臨みて捜露し、文書・賜遺の物を伝送して女王に詣らしめ』とあっただろ?」
「なるほど、一大率は港で積み荷を検査してから送り出していたわけか」
「そういうこと。伊都国の津すなわち牛津を出港した船は、進路を東南に取り、約7km進んで、奴国の港に到着するわけさ。何度も話題にのぼっているが、当時の佐賀県南部つまり佐賀平野は非常に発展していた。なにしろ佐賀平野には日本最大の弥生遺跡・吉野ケ里遺跡があるくらいだからね。まさに『二万余戸あり』と伝えられる奴国の候補地に相応しい地域だったんだよ」
「でも、弥生時代の有明海の海岸線はいまよりもずっと内陸側にあったんだよな? 牛津から東南方向だと、海になるんじゃないか?」
「単純に海抜だけを考えると、確かにそうなってしまうね。だけど、遺跡の分布状況をあわせて考慮した場合、弥生時代も佐賀平野の比較的広い範囲が陸地だったと考えないと辻褄が合わないんだ」
「いわれてみれば、弥生時代に海中だった場所から当時の遺跡が出てくるわけないよな……。それに、佐賀市諸富町には徐福の上陸伝説が残っているんだったね。さすがの徐福も、海中では下船できない……」
「そのとおり。しかもだよ、九州大学の研究によると、弥生時代の有明海の海岸線はかなり入り組んだ形状をしていたようで、とくに現在の佐賀市中心部から南の方向に陸地が大きく突出していたようなんだ。そしてなんと、牛津から東南に約7km進むと、この突出した陸地に到達する計算になるんだよ」

「なるほど、偶然にしては出来すぎているな……。ただね……」
「なにか言いたいことがありそうだね」
「うん、ある。奴国が佐賀平野に存在したとして、志賀島の金印については、どう解釈すればいいんだ?」
通説において、奴国の候補地が那珂遺跡/須玖遺跡の近傍とされている最大の根拠が、志賀島から出土した金印の存在である。
この金印には『漢委奴国王』と刻まれている。通説では、これを『漢の倭の奴の国王』と読み、志賀島の近くに奴国が存在した証拠とみなしている。
つまり、通説には、ミステリーでいうところの物証が存在するのである。
そのため、奴国の候補地を通説以外の場所に求めることは困難だろうと、わたしには思われたのだ。
しかし、Tくんは不敵な笑みを浮かべて「志賀島の金印と『魏志倭人伝』に書かれている『奴国』は無関係だよ」といった。
「多くの研究者が指摘していることではあるけど、『漢委奴国王』を『漢の倭の奴の国王』と読むのは間違いなんだ。古代中国の官印のなかで異民族の国名をふたつ並べた例はない。つまり、『委奴』という表記を『倭』と『奴』という二つの国名を並べたものと解するのは間違いで、『倭奴』という一つの国名と解釈しなければならないのさ。ちなみに、『倭奴』は『匈奴』と対になっている。西の『匈奴』と東の『倭奴』だよ。誰も『匈奴』を『匈の奴』とは読まないのに、なぜ『倭奴』だけは『倭の奴』などという妙な読み方をするのだろうか?」
「いや、しかし金印が出たということは、志賀島近辺が、きみのいう『倭奴国』の中心地だったわけだろ? そこに二万余戸の大国である『奴国』があったと考えることもできると思うけど。『奴』という漢字も共通しているし」
「倭奴国王が金印をもらった西暦57年から、邪馬台国の時代まで、ほぼ200年の時間が経過しているんだ。俺は、西暦57年当時の『倭奴国』と200年後の『奴国』を同一視する根拠を持ち合わせていないし、その必要もないと思うがね」
Tくんは、駄目押しとばかりに、以下のような例をあげた。
数百年前は『京都』が政治の中心地でした。
現在は『東京』が政治の中心地です。
『京都』にも『東京』にも、『京』という漢字が使われています。
したがって、『京都』と『東京』は同一地点に存在します。
これは正しいか?
ぐうの音も出ないとは、このことだった。
わたしは早々に白旗をあげることにした。
しかし、Tくんの進撃はつづく。
不 + 皿 = 盃
「さらに、牛津の東南約7km付近に奴国が存在したと仮定すると、つぎの不弥国にもスムーズにつながるんだ」
と、Tくんは語る。
東行不弥国に至る百里。官を多模といい、副を卑奴母離という。千余家あり。
石原道博編訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝(1)―』
「『魏志倭人伝』には『東行不弥国に至る百里』と記されている。つまり、奴国の比定地から東に約7km行ったところに不弥国が存在するわけさ。さて、地図を見てみると……」
Tくんは、さすがに今回は分かるだろう、とでも言いたげな表情で、こちらを伺う。
どうやら今回ばかりは、わたしもその期待に応えられそうだった。不弥国の候補地は、地図を見れば一目瞭然だったからだ。
「佐賀市諸富町、浮盃だろ?」
Tくんが大きく首肯する。

「そのとおり。徐福伝説の残る佐賀市諸富町、とくに徐福が『浮盃』と名付けた上陸地点。ここ以上に投馬国への『水行二十日』の出発地すなわち船着場たる不弥国に相応しい地はないと思う。しかも、牛津を起点として当時の地形にそって有明海沿岸部を進むと自然に浮盃に到達してしまうのだから、経由地としての妥当性も十分にあるはずだ」
今度はわたしが頷く番だった。Tくんの推理は、『魏志倭人伝』の行程記載に忠実に従うものであると同時に、導き出されたルートも極めて合理的だったからだ。
さらに、わたしには、『盃』という字が『不』と『皿』から成るという点も、『不弥国浮盃説』を後押ししているように思われた。
すなわち『盃』とは、その漢字の成り立ちからすると『皿』の一種である。
そして『皿』の音読みは『ベイ・ボウ・ミョウ』なのだ。
であるならば、
『浮盃』=『浮皿』=『不弥』
という等式が成り立つのではないか?
そんな考えが、わたしの脳裏に浮かんだのである。
わたしが上記の考察を伝えると、Tくんは、
「怪しさの点では、俺の『天之葺根命・伊都国王説』と、いい勝負だな」
と声をあげて笑った。
わたしは「思い付きを述べたまでだよ」と弁明してから、話題をもどした。
「いずれにしても、これで帯方郡から狗邪韓国、対馬国、一大国、末盧国、伊都国、奴国を経て、不弥国まで到達したわけだね。ということは、残るは謎の水行陸行区間のみか」
わたしがそう確認すると、Tくんは
「俺には、その『謎の』という部分がよくわからないのだが……」
と応じてから、
「あとはもう簡単な算数の問題を解くだけで女王国に到着するんだけどね」
と、困ったようにいった。
X= 600
わたしが口にした「謎の水行陸行区間」とは、もちろん不弥国から投馬国、および、投馬国から邪馬台国までの区間のことである。
南、投馬国に至る水行二十日。官を弥弥といい、副を弥弥那利という。五万余戸ばかり。
南、邪馬壱国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月。官に伊支馬あり。次を弥馬升といい、次を弥馬獲支といい、次を奴佳鞮という。七万余戸ばかり。
石原道博編訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝(1)―』
上記のごとく『魏志倭人伝』は、ここにきて突然、行程の表記を『距離』から『日数』に変えている。
しかし、小学校の算数の授業で習ったとおり、『距離』を導き出すためには『時間』のほかに『速度』の情報が必要なのだ(いわゆる『ハジキの法則』)。
したがって、不弥国から投馬国への移動に『水行二十日』を要し、投馬国から邪馬台国までの移動に『水行十日陸行一月』を要しますといわれたところで、不弥国から投馬国までの距離または投馬国から邪馬台国までの距離を特定することはできず、必然的にこれらの国々の位置を特定することも不可能なのである。
この事実は、それこそ「簡単な算数」を理解できればわかるはずなのだ。
しかしTくんは、困り顔のままいった。
「不弥国から女王国までの距離なら、『魏志倭人伝』の記載から計算できるだろ?」
「ああ、なるほど」
Tくんの指摘を受けて、わたしは、ようやく理解した。
『魏志倭人伝』には『郡より女王国に至る万二千余里』と記されている。
すなわち『帯方郡から女王国までの距離は約12000里』と明記されているのである。
したがって、『不弥国から女王国までの距離:X里』は『帯方郡から女王国までの総距離:12000里』から『帯方郡から不弥国までの距離』を引くことで算出できることになる。
ちなみに、帯方郡から不弥国までの各国間の距離は、下記のとおりである。
- 帯方郡~狗邪韓国:約7000里
- 狗邪韓国~対馬国:約1000里
- 対馬国~一大国:約1000里
- 一大国~末盧国:約1000里
- 末盧国~伊都国:500里
- 伊都国~奴国:100里
- 奴国~不弥国:100里
以上から、
X= 12000 – (7000 + 1000 + 1000 + 1000 + 500 + 100 + 100) = 1300
つまり、不弥国と女王国は1300里しか離れていないということを計算によって導き出せるのだ。
なお、『魏志倭人伝』において、対馬国(対馬)から一大国(壱岐)までの距離は『約1000里』とされている。1300里はその1.3倍。対馬‐壱岐間の実際の距離が約70kmだから、不弥国‐女王国間は90km強ということになる。
これならば、九州内に女王国を求めることができる。というわけで、この『不弥国から女王国まで1300里』という仮説は、『邪馬台国九州説』を支持する材料として広く知られているのだった。
「つまり、きみは不弥国から南に1300里、すなわち、浮盃から南に90km強の地点に邪馬台国が存在すると考えているわけだね?」
わたしがそのように問うと、Tくんは、きょとんとした表情になった。
わたしはTくんが図星を突かれて表情を変えたものと思い、少しいい気分になった。
しかし、Tくんから発せられた次なる言葉は、全く予想外のものだった。
「驚いたな……なにひとつ合っていない……」
「はい!?」
Tくんは、ふたたび困り顔にもどって説明しはじめた。
「いいかい、まず『魏志倭人伝』の『郡より女王国に至る万二千余里』という箇所だけど、ここでいう『女王国』は『邪馬台国』と完全同一ではないんだ。それと、『不弥国から女王国までの距離:X里』なんだが、これも1300里ではなく、正しくは600里なんだよ」
X= 600 ?
じつは、『女王国≠邪馬台国』という仮説については、他ならぬ『邪馬台国にいたるみち』でも言及されていた。だから、Tくんにその点を指摘されても特に驚きはしなかった(自分の迂闊さには驚きを禁じ得なかったが……)。
しかし、『不弥国から女王国まで600里』という説は初耳だった。
かくして、Tくんよりも困惑した表情になっているであろうわたしの眼前に、また新たな謎が提示されたのだった。
第六部・完(第七部『邪馬台国・展開編』につづく)
※本作の登場人物であるTくんのモデルは、当ブログ『もなきよの創作プロトタイピング』を運営するわたしの実在の友人です。ただし本作の内容は、あくまでも創作です。